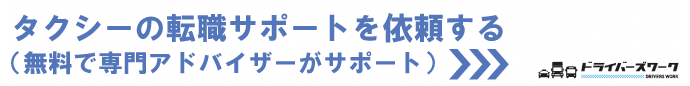乗務員が気になる防犯対策について
 近年、タクシー内で起きる犯罪事件が度々ニュースで報道されています。
近年、タクシー内で起きる犯罪事件が度々ニュースで報道されています。
乗務員への転職を検討している方からも「防犯対策がちゃんとしているのか」など本人のみならず、ご家族からも心配の声があがっています。
タクシーで起きる犯罪事件が増加していることから平成16年より、警視庁でタクシー事業者に「タクシーの防犯基準」を策定することを定めるようになりました。
これにより、タクシー事業者も乗務員の命を守るべく、さまざまな取り組みを始めるようになりました。
今回は、タクシー事業者でどのような防犯対策をとっているのか、乗務員が実際に行っている取り組みについてご紹介したいと思います。
タクシー事業者が取り組んでいる防犯対策
乗務員になろうと思っていて、躊躇してしまう人の中で最も大きい理由が「タクシー事業者の防犯対策がしっかりしているのか?」ということです。
近年、タクシー事業者でもさまざまな防犯対策を実施するようになりました。
多くのタクシー事業者が取り組んでいるのが「防犯カメラの設置」です。文字通りカメラで犯人を映すものになります。この存在に、犯人が気付き犯行に及ぶのを防ぐ効果もあります。
次に多いのが「防犯仕切板」になります。
「防犯仕切板」はさまざまなタイプのがあり、運転席だけ仕切っている物もあれば、最近では助手席から運転席まで全てを仕切っている防犯仕切板も増えてきています。
この「防犯仕切板」の面積が大きければ大きい程、乗務員が安心して業務に臨むことができるので、しっかり「防犯仕切板」が設備されているタクシー事業者がオススメです。
また、最近タクシー事業者で増えてきている取り組みが、タクシーの外(通行人)に知らせる機能です。
どういったものかと言うと、「タクシーの外に付いている行灯の点滅」や「タクシー内にある回送や支払などの表示される表示板が赤く点滅する」など、さまざまな機能があります。
あるタクシー事業者では、乗務員の現場の声を取り入れ「防犯ブザー」が一番周囲に伝える方法として効果的との意見により整備されました。
このようにタクシー事業者の防犯対策は日々強化されています。
乗務員が実際やっている防犯対策
タクシー事業者のみならず、乗務員自身で取り組んでいる防犯対策もあります。
タクシー事業者に入社すると、防犯指導の項目が必ずあります。
これは警視庁から義務付けられているもので、「防犯マニュアル」を周知したり「防犯訓練の指導」などをしたりします。これを受けることにより自らを守る知識が増え、意識も高まります。
またタクシー事業者には「防犯責任者」という専任の担当者もいるところが多いので乗務に不安を感じたり、このような場合はどう対策したらいいのか迷ったりした時は心強い存在になります。
タクシー事業者からも言われるとは思いますが、業務中あまり現金を持たないようにすること、しっかりと相手の顔を見てあいさつをすることで、もしそれが強盗であっても、顔を覚えられたという印象を与えることで、未然に防ぐことが防犯対策としてかなり有効的であると言われています。
地域による防犯対策の違い
タクシー事業者は、乗務員を守る義務があるので、これらの防犯対策をちゃんとしているタクシー事業者を選ぶ必要があります。
一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会の調べによれば、地域によってタクシーの犯罪件数に差があり、関東では「防犯仕切板」の装着率が78%に比べ、関西では16%と低くなっています。
その影響か近年では犯罪件数が関西方面で頻繁に行われているという報告もあります。
以上のことからも分かるように、防犯対策がしっかり行われている場所を選ぶことが乗務員自身ができる最も重要な防犯対策なのかもしれません。
参照元:https://www.drivers-work.com/column/knowledge/taxidriversecurity/