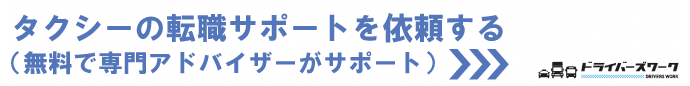乗務員の業務に差支えない飲酒量とは
 乗務員さんの中にももちろんお酒が好きという方は多くいらっしゃいます。
乗務員さんの中にももちろんお酒が好きという方は多くいらっしゃいます。
しかし乗務員という仕事はお客さんの命を預かる大切な仕事ですので、深酒をして次の日の業務に支障をきたしてしまうほど飲むのはもちろんNGです。
とはいえ、いったいどれぐらいの飲酒量までならば、次の日のタクシーの乗務に問題がないのでしょうか。
意外と知らない飲酒と運転についてお話します。
道路交通法よりも厳しいタクシーの飲酒基準
法律によって、タクシー会社では乗務員に対してアルコール検知器で呼気中のアルコール濃度を測定することが義務付けられています。
道路交通法におけるいわゆる「酒気帯び運転」は血中アルコール濃度0.3mg/mlもしくは呼気アルコール濃度0.15mg/Lが基準値とされていますが、タクシー会社では少しでもアルコールが検出されれば乗務禁止とされています。
そうはいっても、お酒好き乗務員さんにとっては、一体どれぐらいまでなら飲んでも翌日の乗務に問題がないのか、その飲酒量やアルコール検知器に引っかからないために飲酒後何時間あいだをおけば良いのかは気になるところです。
アルコールが抜けるまでの時間を知ろう
日本人の成人男性30~50代の平均体重である約68kgの方の場合、缶ビールや缶チューハイ1本(350ml)の場合、体からアルコールが抜けるまで約2時間かかるといわれています。
また、缶ビール2本の場合は約4時間とアルコールの摂取量に比例して、アルコールが抜けるまでの時間は長くなるものだとされています。
日本酒の場合は1合(180ml)で3時間、2合で6時間、ワインの場合はワイングラス1杯(120ml)で3時間、2杯で6時間かかるとされています。
ただアルコールが抜けるまでの時間は、その人の体重や体質、遺伝や体調にもよりますので、一概に上記のような計算になるとはいえませんが、目安にしておくとよいでしょう。
タクシー乗務開始までの9時間で抜けるお酒の量とは
あるタクシー会社では、タクシーの乗務開始9時間前までの飲酒をOKとしているところがあります。
しかし、先ほどもお話したとおりアルコールが抜けるまでの時間というのは、お酒の量によって変わってきます。たとえば乗務開始の9時間前の時点でどれぐらいまでなら許容範囲となるか計算してみましょう。
- ビールや缶チューハイ・・・4.5本(350ml/本)
- 日本酒・・・3合
- ワイン・・・グラス3杯
いかがでしょうか。思ったより多かったでしょうか?少なかったでしょうか?
こちらはあくまで一例ですが、タクシー会社の規則で9時間前までの飲酒が認められていたとしても、ビールを5本も6本も飲んでしまうと、乗務開始時のアルコールチェッカーでの測定でアルコールの反応が出てしまうことになります。
お客様の安全を守るためにも、節度を持った飲酒が大事だと言えます。
1日の飲酒量はアルコール20gまでが重要
厚生労働省の発表によると、日本人の健康に影響が出ない範囲の飲酒量として、純アルコールで1日20gまでとしています。
これは、ビールや缶チューハイですと500mlのロング缶1本分、日本酒ですと162ml(1合は180ml)となります。アルコールチェッカーで問題がないといっても、お酒の飲みすぎで体を壊してしまっては元も子もありません。
お酒は少量であればストレス発散や気分転換によいものですが、度を過ぎてしまうと健康を害するだけではなく、乗務員の場合はお客様の命を危険にさらす、さらに事故を起こしてしまった場合には、会社にも多大な迷惑をかけてしまうリスクがあります。
プロの乗務員としての自覚と責任をもって飲酒をするように心がけたいですね。
参照元:https://www.drivers-work.com/column/knowledge/alcoholcheck/